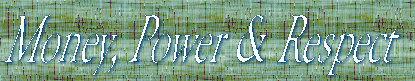
SECT. ONE: MONEY
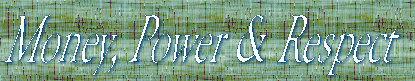
SECT.
ONE: MONEY
「20年間、僕はこの日を待っていたんだ…やっと、やっと夢が叶ったんだ…」
1996年NBAドラフト、第4位でミルウォーキー・バックスに指名されたステファン・マーベリーは指名直後の記者会見で大粒の涙をこぼし、こう語った。たかがNBAドラフトに指名されたくらいで大袈裟な、と思う人もいるかもしれない。しかし、彼の育った境遇を知ればそう鼻であしらうこともなくなるだろう。
ニューヨーク・ブルックリン。ステファンはそのブルックリン地区の中でも南端の半島状に突き出たコニーアイランドという場所で育った。「ニューヨーク」と聞けば普通の日本人はマンハッタンの華やかさを想像するであろうが、イーストリバーを挟んだ対岸にあるここでは「ゲットー」と呼ばれるスラム街の中に最低所得者層の人々がひしめき合い、日がな一日の生活を送っている。
人種・民族によって今でも棲み分けという「差別」が厳然と存在しているアメリカ合州国では、こういった所に住む人々はアフリカン・アメリカンやヒスパニック系移民が多い。彼らはよほどの幸運がない限りブルーカラーの職に就くことを余儀なくされ、物価だけは一人前に高いニューヨークで生きていかなければならない。その労働と生活のあまりの過酷さにドロップアウトする人々も当然出てくる。彼らは街に溢れるドラッグやアルコールやギャンブルの誘惑に溺れ、家に戻ることもなくさまよい歩く。置き去りにされた子供達は路頭に迷い、盗みや売春に走る。巷ではレイプやリンチといった暴力が蔓延し、ごく些細なことで銃撃戦が起き、標的以外の何の罪もない人が流れ弾に当たって命を落とす。夜でも平気で女性が一人歩きできるような日本から考えれば信じられないかもしれない。しかし、これがゲットーの現実なのだ。
幼い頃からこのような場所で育っていれば誰だって「いつかはこんな場所を抜け出してやる」と思うだろう。しかし、そのためには一心不乱に何十年も働き続けなければならない。気の遠くなるような月日を労働に費やすことに我慢が出来ない人々はすぐに大金にありつける方法を何とか模索しようとする。ゲットーにおけるその方法は3つ。ドラッグの売人になること、自分の息子をプロスポーツ選手にすること、ショービジネスの世界に入ること、だ。
マイノリティのプロスポーツ競技への参加が認められ始めた70年代頃から、プロスポーツはメディアの力を借りて「テレビ観戦」という新しい市場を定着させるようになり、84年のロス五輪で一気に開花した「テレビスポーツ観戦」という目玉商品によってプロスポーツの放映権料はその運営にとって欠かせないものになった。それに伴い、プロチームに所属するスポーツ選手の契約金も莫大な額に跳ね上がってきた。こんな状況の中で汲々とした生活に辟易しているゲットーの人々はこう思うのだ。「もし、自分の息子がプロスポーツ選手になってくれたら…」好都合なことにスポーツはストリートに溢れる「遊び」の中で最も害がないものだ。スポーツをやることで仲間との協調性がつき、ルールを学ぶこともできるのではないだろうか。こうして子供達は知らず知らずの内に大人達の様々な思惑の中でスポーツを始めていく。
ステファンは5人の兄弟の4番目に生まれた。上の兄達は皆ストリートでバスケットボールをして育ち、運動能力に恵まれてニューヨークのミドルスクールやハイスクールではバスケットのスター選手として活躍した。大学バスケットNCAAでカンファレンス得点記録を樹立した者もいる。普通兄弟全員がこのように華々しい成績を残すことは殆どない。故にマーベリー家と父ドンは低所得のゲットーに暮らしていながら特別な尊敬が払われてきたのだ。
しかし、華やかなハイスクール・バスケットの成績とは裏腹に、兄たちは途中で挫折したり、NBAにドラフトはされてもなかなか活躍できなかったりで家族はなかなか裕福にならない。そこに現れたのがステファンだった。彼はすでにミドルスクール時代からその才能を顕していた。「今度こそ」と親の期待や兄弟の期待、周囲の期待は嫌でも膨らむ。ブルックリンを仕切るボスまでもがステファンに車を買ってやり、ある時ステファンが事故を起こして車を壊してしまっても無料で直してやった。彼はまさに「金を生む鳥の雛」扱いだったのだ。幼いときから家族の、いや、近隣のブルックリン一帯の関係者の金に踊らされた期待を一身に背負ってバスケットをしなければならなかったステファンに失敗は許されなかった。NBAにドラフトされるというゴールの瞬間までの20年間、彼は自分は兄たちのようにはなりはしない、家族を裕福にしなければならないというプレッシャーをずっと受けつづけていたのだ。おそらく彼は総合4位という非常に高いドラフト順位で自分の名前を呼ばれた時、長いこと心の中にためてきた重荷がやっとのことで取り除かれる思いでつい涙がこぼれてしまったのではないだろうか。
ここで取り上げたマーベリーのみならず、アメリカの大都市のゲットーに生まれたアフリカン・アメリカンの子供の多くは一度はNBAという夢に憧れ、バスケットのゴールに向かう。プレイグラウンドでのストリート・バスケットボールで年上の相手を負かすようになってくればいよいよその夢はいや増す。彼らの中には父がいないシングルマザーの家庭の子も少なくない。母親は子供達を養うために朝早くから夜遅くまで働きに出て、疲れ果てて帰ってくる。男の子にとって最初の「アイドル」である母親のそんな姿を見て、「少しでも母さんを楽にさせてあげたい」と思うのは自然な気持ちだろう。そして彼らは「バスケットで有名選手になってお金持ちになれば今のような悲惨な生活はしなくてよくなるんだ」と考え、更にバスケットに打ち込むことになる。
また、ゲットーで深刻な問題となっているのが成人男子の絶対的な不足だ。多くの少年達は18歳になるまでにストリートの犠牲になって死んでしまう。その理由はストリートで始終繰り返される銃撃である場合もあるし、薬物中毒である場合もある。ともかく男の子が少なければ女の子は残された男の子を奪い合うことになり、より「有利な立場」に立とうと先を争って子供を作るところにまでエスカレートする。近所で少しでも名の知れたスポーツ選手ならば女の子達は目の色を変えてモーションをかける。子供が出来てから後、万が一その父親がプロスポーツ選手になればゲットーでは考えられないくらい高額の養育費をふんだくることができるからだ。少年達もまだ子供を育てていくことの苦労にあまり現実感をもてない、ただ興味本位で女の子と遊んでみたい年頃だ。グルーピーの女の子達から色っぽい仕草などされたら我慢するなという方がどだい無理な話だろう。何年か経って、その産まれてしまった子供の母親から養育費や慰謝料をごまんと請求される段になってしか彼らは自分の過ちに気づくことができない。そして彼らはここでも「金をもたらす期待」に追われることになるのだ。
SECT.
TWO: POWER
「カネは私にはふさわしくはないものだ」
1945年から1975年までの29シーズン、UCLAでコーチとして数々のスター選手を育て、NCAA7連覇という以降破られることは殆ど不可能であろう偉業を成し遂げたジョン・ウッデンはこう言ってUCLAのコーチ宛に提示されたシューズ会社との契約を一蹴した。彼が主宰する「ジョン・ウッデン賞」は毎シーズンの最高のカレッジバスケットボールプレイヤーに与えられる賞として有名だ。しかしそのジョン・ウッデン賞を受けた3年生以下のプレイヤーは1人を除いて全てアーリーエントリーを決め、4年の年限を待たずにプロ入りしている。そんなプレイヤー達を前にして毎年のようにウッデンは「金が若い選手達を良くない方向に走らせている。何かが間違っているとしか思えない」と嘆息する。
このような意見は何もウッデンに限らず、NCAA関係者やNCAAのファンにも広く見られるものだ。カレッジバスケットボールを愛する者としてプレイヤーをプロに「とられて」しまうのはやはり少し寂しい気がする。しかし、NCAAは運動部に所属する学生達にそれに見合うだけの処遇をしているのかと問われて胸を張ってイエスと答えられる人間がどれほどいようか。
「現代にはNCAAというプランテーションがある。そこで働くステューデント=アスリートという名の労働者達は役人達に監視されてほんのわずかの賃金で働かされているのだ」
こう評したのは1951年から1987年までNCAAのエグゼクティブ・ディレクターを務めたウォルター・バイアスだ。NCAAの中枢部にいる間に様々な時代の変化とそれにつれて起こってきたカレッジスポーツの問題にもろに直面してきた彼が言うからこそ、この言葉は現実味を帯びてくる。
スポーツをする学生に対して初めて全額保証の奨学金が与えられるようになった1956年当時、大学に通うことは資金的に非常に困難だった。また、スポーツも今のように大々的にテレビ中継がされるわけでもなかったから、「スポーツ特待生」として奨学金を受けることは一つの特権たり得た。しかし、メディアがスポーツを「視聴率が稼げる素材」として注目し始め、プロスポーツのみならずカレッジスポーツの世界にまで手を広げ始めたとき、その特権はもはや特権ではなく、ただの足枷と化してしまった。
「僕はコネチカットにいた大学時代、食費として一日に11ドルしかもらえなかったんだ。CBSやESPNみたいな放送局が一試合に何十万ドルも僕たちの試合で儲けてる一方でね」
こう語るのはNBAのミルウォーキーバックスで活躍中のレイ・アレンだ。
アパート住まいのフルに奨学金が出ているプレイヤーに対して大学側が一ヶ月に支払う生活費はたった500ドル。その中から家賃や食費、光熱費を払ってしまえば残る金額は音楽CD一枚分にも足りない。一方購買部ではその大学のスタープレイヤーの背番号がついた何十ドルもする(中には100ドル以上するものもある)ジャージが山とおいてあり、学生や試合を見に来た客はそれを買い込んでいく。しかし、当のプレイヤー達は自分自身のジャージすら購買部で買えないくらいの生活をしているのだ。
そんなぎりぎりの生活をしていながら、彼らはメディアの喧伝のせいで毎日注目を浴びて暮らさねばならない。注目されることが財産であり、ステイタスであることはアメリカ合衆国の人々に多く見られる考え方だが、プレイヤー達は日がな一日注目を受け続け、プレイベートな時間が殆ど持てない状況の中で非常に苦しい生活を強いられ、周囲の視線を気にしながら授業に参加しなければならない。これは既に「財産」などではなく、拷問の類に入るのではないか。メリーランド大に2年間在籍した後にアーリーエントリーし、NBA入りしたジョー・スミスはそんな「見せ物パンダ」のような生活に耐えられずにプロ入りを決意したという。彼らは「ステューデント=アスリート」(運動部に所属しながら勉学を修める学生)ではなく、「アスリート=ステューデント」(スタースポーツ選手で、学校にちょっとだけ勉強に来ている人)として、自分の運動能力を大学という「権力」を持った一つの企業体にほしいままに搾取されているプロレタリアートと表現しても言い過ぎではなかろう。
更にアメリカの殆どの大学は一見して判るように白人の比率が通常の人口比に比して格段に多い。これは如何ともし難い人種による平均的な所得の格差を厳然とあらわしている。前節でも少し触れたがアメリカ合州国は人種や民族集団、宗教集団によって「棲み分け」がなされている。それまで殆どが黒人であるゲットーの中で暮らしていた(もしくは黒人が多く集まるコミュニティの中で暮らしていた)黒人の少年達にとって、白人ばかりの大学に入学して生活していくことは、非常に精神的に負荷がかかることだ。このことは日本という国の中で生きている人の大半には実感できないことかもしれない。我々の中には「同じ言葉をしゃべって同じ国の中に生きている人間なのだからそう大して苦労はしないはずだ」という思いこみがあるからだ。しかし合州国は違う。確かに彼らの使用言語としてカテゴライズされるのは英語だが黒人のコミュニティで話されているのは我々が「アメリカ英語」としてよく見知った白人英語とは全く異なっている。ある白人の教授が講義の中で黒人社会で使われている言葉を紹介した時に、その用法について聴講していた黒人学生の方が詳しく説明できた、という例もあるぐらいだ。日本的な言い回しで語ることが許されるならば、黒人のコミュニティは白人中心のアメリカ社会の中では「内なる外国」なのだ。そのような異なった文化の持ち主である黒人選手が白人社会の典型である大学(無意識のうちに白人の文化で物事が語られている場)の中で生きていくことは、留学生がアメリカの大学で生きていくことぐらい難しい。
それでも大学に通って単位を取得し、学士号を得ることはやはり「特権」であり、スポーツに秀でた人物が多少勉強は出来なくても大学で学士号を取ることができることでその「権力による搾取」は充分報われるだろう、と考える向きも多かろう。しかし、そこにも問題点は数多存在する。
現在NBAニュージャージーネッツで活躍するジム・マッキルベインはマーケット大学在学中、「4年で卒業するために」専攻をビジネスからコミュニケーションに強制的に変更させられた経験があるという。大学側にとってその大学チームに所属した運動選手が卒業していく「卒業率」というのはその大学の評判を高め、より素晴らしい運動選手をリクルーティング(獲得)するという意味でも一つの大きな指標となっている。その卒業率を少しでも上げるために大学側は運動部の学生に「簡単な専攻」を取るように「指導」するのだ。そしてそれが本当にその学生が望んでいる勉強なのかどうかは彼らの頭にはない。
「『勉強なんかしてないでフットボールをやれ』なんて面と向かって言うコーチなんていないけど、実のところはそう言ってるも同然なんだ。」
ウェストヴァージニア大学でオフェンシブ・タックルとして活躍し3年でアーリーエントリーをしてNFL入りしたソロマン・ペイジはこう語る。
「フットボールは本当にたくさんの時間とエネルギーを要するものだから勉強は二の次にならざるを得ないんだ。月曜日から金曜日まで、2時半から6時半まで僕はチームメイトと一緒に練習をしたり、ウェイトリフティングをしたり、ビデオを見て分析したりしている。オフシーズンだろうが、それはたいして変わらない。冬や夏だって練習が殆ど強制されているようなものさ」
ペイジはフットボールの選手であるが、運動部に所属する他の学生についてもこの状況は全く同じだ。彼らはスポーツを強制されてやっているも同然の状態なのだ。たとえ彼らの中に向学心に燃えた人間がいて、卒業後の安定した専門的職業が保証される法律や医学を入学した大学で専攻しようと思ったとしても、その殆どは大学側によって拒否され、「スポーツに支障がないかぎりでの」専攻選択が許されるだけなのだ。現在NFLミネソタ・ヴァイキングスにいるロバート・スミスはオハイオ州立大学在学中「おまえは勉強しすぎだ」とアシスタントコーチにたしなめられ、それが原因で同大学を退学した。学問を修め、より深い専門的知識や判断力を養うことが第一目的の大学で「勉強してはいけない」という指導がなされるその本末転倒な状態には、もう怒りを通り越して笑ってやり過ごす他ない。
そのくせ、大学側は評判を気にして(「この大学はステューデント=アスリートにちゃんとした教育を受けさせています」という評判は大学にとって最高の財産であるからだ)学生の成績をなんとか優秀に保とうとする。1999年の4月に明るみに出たミネソタ大の大学ぐるみでの運動部学生の成績捏造はこうした経緯を考えれば起こって当然と言えなくもない。実際、このような成績の嵩上げは成績優秀な運動部を抱える大学では日常的に起きていることだともいわれている。
若いアフリカン・アメリカンの男子学生のアーリーエントリーを非難する人々は、このような大学の運動部の歪んだ現実をどれだけ知っているのだろうか。プレイヤーにとって全てが逆境であるような現状を知っても4年間在籍して耐えろと言えるだけの資格があるだろうか。そして、日本の人間である我々がアメリカのメディア(その多くは白人によってコントロールされている)の論調に影響されてアーリーエントリーを短絡的に批判することは、無意識のうちに自分自身を白人マジョリティの側に立たせてしまっている「バナナ」な精神構造を露呈することになりはしないか。
合州国は単純には割り切れない、複雑な権力構造をもった国だ。我々はそのことをもっと知る必要があるだろう。
CHAP.3:
RESPECT
しかし、それでも私は思う。「不必要なアーリーエントリーはしない方がいい」、と。これは最近増えている高校生からの直接のNBA入りについても同様だ。
運動部の奨学金を受けて入ってくるプレイヤーの多くはアフリカン・アメリカンだ。ゲットーで暮らす黒人達の多くが高校を中退して働いたり、浮浪者になっている現状から考えると、彼らにとっての大学の学位の価値は、白人に比べて相当貴重なものだ。大学を卒業したとなれば職も段違いに見つけやすい。彼らが社会人として活躍することによって沈滞したコミュニティが再び活気づく可能性だって大いにあるのだ。彼らはスポーツを通してコミュニティを支えることや、コミュニティの「顔」としていつも振る舞わなければならないことをよく知っている。そんな彼らが大学を途中でやめたり、高校でドロップアウトしたりすることはもう本人だけの問題ではない。彼らがそうすることで、コミュニティに暮らす人々は「どうせ誰がやったって状況は良くならないさ」と再び無気力に陥ってしまうのだ。至源の昔、パンドラの箱は開けられてしまった。しかし、箱に残った最後の「希望」を守るのは権力にまみれた政治家でもなく、ヤクにまみれた売人でもなく、彼らスポーツ・プレイヤーなのだ。
しかし同時に彼らは自分たちに向けられた「尊敬」のまなざしがほんの束の間の幻影であることを知らなければならない。地元の高校で活躍し、将来を期待されている内の若い少年達は自分の現在の実力だけでなく、「可能性」という非常に不確かな、しかし魅力に溢れるベールを纏っていられる。しかし、大人になってある程度の先が誰の目にも明らかになればそのベールは一瞬のうちにして剥ぎ取られてしまう。「期待の星」だ、「ザ・マン」だともてはやされていた彼らもやはり「二十歳過ぎればただの人」なのだ。そんなとき、大学の学位があるとないとでは職の可能性がかなり違う。「バスケットボール」という印籠を取られてしまっても、大学に行って学位を取得したことで彼らにはもう一つの道が開かれる。そして、バスケットボール人口から考えればその道を選ぶ人のほうが遥かに多いのだ。「俺は違う。俺は何とかやりとげてやる」という心意気は否定はしないが、プロ選手として生計を立てることができるのは、バスケットを楽しむ人の中のほんの一握りだということも知っておいた方がいい。万が一プロ選手になれたとしても、バスケットボールのプレイヤー生命は各プロスポーツの中で最も短く、多くのプレイヤーが30歳を過ぎるか過ぎないかで引退していってしまう。人生70年としてあとの残された40年、彼らが過去の遺物だけで生き長らえていくことなど、考えるだけ無駄というものだ。
それに、彼らは高校時代までバスケットボールしか知らない、知らされない生活の中で暮らしてきた。大学はそうした彼らにとって「新しい世界」との邂逅の場たりうるのだ。それまでのゲットーや地方の狭いコミュニティの生活しか知らなかった彼らは、大学に通うことによって全く違う生活をしている人たちに出会い、自分がいかに狭い価値観で縛られてきたかを少しでも知る可能性が与えられるのだ。たとえ彼らが見た大学が前節で述べたように腐敗しきっていたとしても、少なくとも「こういう世界にはしたくない」という反面教師にはなるではないか。
また、多くの高校では組織だったプレイを本格的に学ばせることが出来ない。そんなところに素晴らしい運動能力と可能性を持ったプレイヤーが入ってきても、コーチに出来ることと言ったら、そのプレイヤーが一番目立つようにお膳立てすることぐらいだろう。高校レベルまでは、個人能力だけのプレイスタイルでもある程度通用してしまうからだ。彼らは組織だって、相手の、そして味方の動きを見てプレイをする事を殆ど知らないでちやほやされ、NBAへのアーリーエントリーを決めてしまう。この傾向は彼ら自身はおろか、現在のNBAの質をも下げてしまうことになりはしないか。確かにNBAはルール的に個人能力に主眼を置いたものとなっているが、だからといって筋力だけではチームプレイはできないし、そうした力任せのプレイスタイルには自ずと限界がある。頭を使わず、ただひたすら力の限りダンクするだけの「見せ物」を「世界最高」と銘を打ってみても、スプリングフィールドのネイスミス博士は決して「これがバスケットボールだ」とは認めないだろう。
これに対し大学バスケットは個人能力というよりはチーム力に重点を置いており、高校のレベルでは教えきれない、システムに対する理解を補うには非常に良い場所だ。将来的にNBAに入るとしても、システムを知っているのと知らないのとでは、その後のプレイヤー人生に大きく差が出る。若い頃はスターターで看板選手だったとしても、年を取れば必然的にベンチスタートになってロールプレイヤーとしての役割が期待される。こういう時、自分の所属するチームのシステムや戦略を正しく理解するだけの素地がなければ、後に待っているのは冷たい「戦力外通告」だけだろう。
確かにプロ・バスケットボールの世界は華やかで収入も非常に多い。我々がNCAAの抱える様々な歪みを知れば知るほど、アーリーエントリーをする学生達を引き留めることは出来なくなってくる。しかし、敢えてこういう忠告だけは出来るだろう。
「君たちは素晴らしい能力を持っているし、しかも若い。しかし、君たちだって普通の人間だ。結婚もすれば病気にもなり、家族を養ってもいかなければならない。もしこの先君たちが『バスケットボール』という魔法の効き目がなくなってしまったら、君たちはそれでも『普通の人』として、普通の人並みに暮らしていくことができるのだろうか?」
ドキュメンタリー映画『フープ・ドリームス』に主演し、自らの紆余曲折の高校時代をありのままにスクリーンの前にさらけ出したウィリアム・ゲイツはプロ・バスケットボールへの道を追い続け、そして違う道を敢えて選んだ一人として次のようなメッセージを残している。
「もし究極の目標が“フープ・ドリーム”、つまりプロとしてバスケットボールをすることなら、それはすばらしいことだ。ただ言いたいのは、その途中、夢に到達するまでの間に達成したことにも目を向けてほしいということ。卒業証書や大学の学位、そして多くの人との出会い。そういったことも誇りに思ってほしい。…自分がバスケットボールに使われるのではなく、バスケットボールを使うようになることなんだ。」
カネ、権力、そして虚栄。多かれ少なかれ、NCAAやNBAはそうした面をもたずには成り立って行かない。しかしその中に巻き込まれるプレイヤーは、被害者ぶってばかりではいけないだろう。勿論、一人の個人として出来ることは限られる。しかし、ゲイツが言うように、自分が「使われる」のではなく、自分が「使ってやる」と思うだけで、積極的に貢献できることはいくらでも見つかる。その時こそ、"Money, Power & Respect"は「豊かさ」になり、「周りの人にもたらされる影響力」になり、「人々の尊敬」となるのではないだろうか。
Copyright:WOG
Go Back Home